 › かりゆしぬあしび › 模合とは?
› かりゆしぬあしび › 模合とは?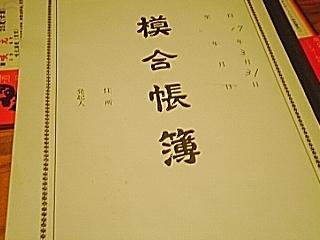
模合の起源は琉球王国の尚敬王の時代まで遡ることができる。当時の三司官の蔡温は、士族の門中間の相互扶助を図るために制度化した。 当時の模合は、貨幣ではなく農産物などの食料品などが模合の対象であった。変り種としては「労働力の提供」というのもあった。 明治時代になり、各地に銀行が設立されるようになるが、一般庶民には遠い存在であったため、庶民向けの金融制度としての地位を確立した。営業化して無尽会社に成長するものもあった。 しかし、中には「相互扶助」の目的から大きくかけ離れた利殖目的の模合や模合の責任者が金だけ集めて雲隠れする詐欺的模合[1]が現れたり、模合が破綻[2]して企業倒産や破産者が続出するなど、現在に至るまで沖縄県では大きな社会問題となっている。 現在でも沖縄県では「模合帳」という帳簿が市販されている。
この記事へのコメント
奥が深いですね。助け合いの絆の証ですねo(^-^)o
Posted by あかり at 2011年05月01日 20:48
あかりさんへ
沖縄の伝統文化、風習に匹敵すると思いますよ!
沖縄の伝統文化、風習に匹敵すると思いますよ!
Posted by かりゆし企画 at 2011年05月02日 04:14
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。












